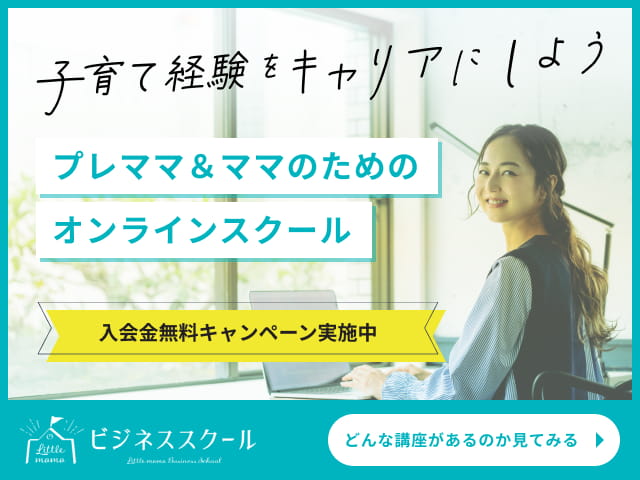キャリアWeb記事
知っておこう!新生活での子どものストレスサインとその対処法6つ

新生活が始まり、数ヶ月がたちました。入園や入学で環境や生活リズムが大きく変わることで、子どもが体調を崩したり、わがままになったりしませんか。
一見困った行動も、実は新しい環境からのストレスサインかもしれません。
本記事では子どものストレスサインについてと、子どもが安心して新しい環境に適応するために親ができるサポートについて、筆者の経験も踏まえご紹介します。
目次
新生活で現れる、子どものストレスサインとは

子どもは環境の変化にとても敏感です。
大人でも、新しい環境にストレスを感じる人は多いのではないでしょうか。
幼い子どもは自分の気持ちを言葉でうまく表現できないため、ストレスを感じた気持ちを表現できず、疲労が蓄積され行動や体調に変化が現れてしまうことも。
1.ストレスサインってどんな症状?
ストレスサインとは、ストレスが原因で、からだと心に現れる症状のことです。
ここでは、子どもに起きるストレスサインを3つの分類に分けて紹介します。
ストレスの感じ方や耐性は個人差があり、症状も様々ありますが、一般的なものとして以下のような症状があります。
行動の変化
- 学校に行きたがらない
- 家族に反抗的になる
- ささいなことで物を壊したり、人に攻撃的になったりする
- 親のそばから離れない、強い甘えがみられる
からだの反応
- 食欲がない、あるいは過食になる
- からだのかゆみや痛みを訴える
- 夜尿が始まる、あるいは増える
- 以前にはみられなかったチックがでたりチックが激しくなる
表情や会話
- ささいなことで泣く
- 元気がない
- 笑わなくなる
- 喜怒哀楽が激しい、あるいは無表情になる
一部抜粋になりますが、おしゃべりな子や口数の少ない子など、子どもの性格や発達特性にもよってストレス反応も変わるため、子どもをしっかり観察することが大切になります。
2.子どもの年齢によって変わるストレス
子どもの年齢や成長発達段階で主なストレスの内容に違いもあります。
| 幼稚園や保育園 | 「母子分離不安」で大好きなママと離れることに強い不安や緊張状態になる時期。集団で過ごし、自分の思い通りにならないことでストレスを感じる。 |
| 小学校入学 | 「母子分離不安」だけでなく集団の中で規律性を持って過ごすことや、授業が始まることへの不安が出てくる時期。 |
| 小学校進級 | 「新しいクラスでの友達付き合い」「課題の量の増加」「授業の難しさ」など人間関係や優劣についてなど、ストレスの内容が大人に近づいてくる。 |
何について悩み、ストレスを感じるかは子どもによって違います。
効果的な対応をするために、ストレスの原因を把握してサポートしていく必要があるのですね。
3.筆者の子どもの場合
筆者は小学生の子どもが3人いますが、幼稚園入園時は夜泣きが増えたり、親に抱っこを求めることが多くなったのを覚えています。
まだ自分の気持ちを自分自身で理解できないことも多いので、子どもの様子からストレスの度合いなどを把握することが多かったです。
小学校入学や進級では、兄弟喧嘩が増えたり腹痛や頭痛を訴えたりする時期もありました。
成長するにつれて、何が不安なのか自分の口で言えるようになってきたので対応もしやすくなったように思います。
子どものストレスサインに対して、家庭でできる対策6選

子どもがストレスを抱えている時に有効なことは以下の6つになります。
- 子どもの気持ちを大切にしたコミュニケーションを心がける
- スキンシップを増やす
- 子どもの好きなことをする時間を増やす
- 安心できる環境を整える
- 生活リズムを整える
- ストレスの原因を解消する
それぞれ解説していきます。
1.子どもの気持ちを大切にしたコミュニケーションを心がける
子どもにママやパパから声をかけ、話を聞いてあげましょう。
その際は子どもが話し出したら口を挟まず、最後まで話をきくことが大切です。
また、無理に聞き出すのはNGになります。
簡単なようでこれが意外と難しく、筆者はいつも子どもの話の途中で口を挟んでしまうことが多いことに気づきました。
最後まで聞いてあげることで、子どもの気持ちを尊重でき、親子の信頼関係が深まります。
子どもが自分の気持ちを整理しながら話す練習にもなるので、時間に余裕を持って話を聞きましょう。
子どもが話をしてくれた時は「そんなことがあったんだね」「話してくれてありがとう」など肯定的な言葉を伝えることで、子どもは安心することができます。
話をするときは寝る前のゆったりした時間など、子どもが安心できるタイミングを選びましょう。
またママやパパもテレビやスマホから少し離れるなどして、子どもが話をしやすい空気を作っておくことも大切です。
2.スキンシップを増やす
スキンシップをとることで愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌され、安心感や幸福を高めます。
「慣れない新しい環境でよく頑張ったね」、と子どもにハグをしてあげましょう。
その効果は、ハグをする方とされる方のどちらにもあるので、子どもとママの新生活での心とからだの疲れを癒してくれること間違いなしです。
「手を繋ぐ」「抱っこする」「お風呂に一緒に入る」「一緒に寝る」など小さなことでも十分です。
もしスキンシップを嫌がる子であれば、一緒に何かをする時間を設けたりコミュニケーションをとることでも良いでしょう。
3.子どもの好きなことをする時間を確保する
好きなことをすると気持ちがリフレッシュされ、ストレス軽減につながります。
大人がストレス発散に好きなことをするのと同じです。
外で遊んだり、絵を描いたり工作をしたり、興味のある場所や遠くまで出かけるのも気分転換になります。
筆者のおすすめは自然の中でからだを使って遊ぶことです。
きれいな景色や気持ちのいい空気は子どもだけでなく家族みんなを癒してくれますし、子どもと一緒に遊ぶと気持ちが一気に明るくなります。
4.安心できる環境を整える
子どもにとって、自宅が癒され安心できる場所であれば、自宅でしっかり休んでまた頑張ることができます。
子どもが安心して過ごせる場所にするために、ママとパパのからだ調も整えましょう。
子どもの1番の味方であるママやパパが肯定的に接してあげることで、幼い心に安心感が芽生え、ストレスの軽減に繋がります。
忘れがちですが、ママやパパも実は大きなストレスを受けていることが多いです。
そのため子どもだけでなく、自分自身のケアにもしっかりと目を向けましょう。
5.生活リズムを整える
新しい環境で過度な緊張状態で過ごしているので、子どもは体力も消費しています。
またストレスが蓄積されることで自律神経が乱れ、免疫力の低下を引き起こすことも。
しっかり睡眠時間の確保とバランスの良い食事は、体力回復と免疫力を高めてくれます。
ストレスを強く感じている時こそ、規則正しい生活を心がけましょう。
6.ストレスの原因を解消する
子どもをよく観察して、新しい環境の中でも、何に強いストレスを受けているのかキャッチしましょう。
環境の変化など解消することができないことは、子どもをいたわり支える必要があります。
しかし「友達とのトラブル」「習い事も重なり体力的にしんどい」などストレスの原因に具体的なものがあれば、解決できるかもしれません。
学校や地域のサポートを上手に活用しよう

保護者以外の大人も子どもの状態を把握しておくことは大切です。
1.学校や園と情報を共有しよう
まずは学校や園と情報を共有しましょう。
子どもの特性や性格を知ってもらい、学校や園での様子を聞くことで、適した対応が可能になります。
小学校では、希望すればスクールカウンセラーの先生に相談や面談もできます。
筆者は実際にカウンセリングを受け、子どもが学校に対して前むきに登校できていないことや、家で家族に対して怒りっぽくなっていることなど、不安や辛かった話を聞いてもらいました。
カウンセラーの先生が側で寄り添って話を聞いてくれたことで、安心感がもて、本やネットで情報を読むよりも、心が軽くなりました。
2.保健センターや発達支援センターで相談
地域によって、保健センターで健康相談や育児相談をしています。
子どもの発達については発達支援センターや家庭児童相談所などでも相談もできるので、不安がある方は調べて参加するものいいかもしれません。
3.小児科を受診
症状の原因はストレスだけでない場合もあります。
中には胃腸炎などの感染症の場合や自己免疫疾患や甲状腺などのホルモン異常などの病気が隠れている可能性もゼロではありません。
また食べれない期間が長く、体重が減った場合なども注意が必要です。
症状の程度や期間が長く続く場合は一度小児科を受診して、別の病気が隠れていないかみてもらうと安心ですね。
急がなくて大丈夫!徐々に新生活に慣れていこう

人間が生きていく上でストレスはつきもので、適度なストレスは子どもの成長に必要です。
環境の変化は人生の中で何度もやってくるので、新生活に慣れるまでの経験はその子にとって貴重なものになるはず。
できるようになったことを子どもに直接伝えてあげると、自信がつくことでしょう。
筆者の子ども達は、歳を重ねるごとに新しい環境に対してストレスが軽くなっている印象を受け、成長を感じることが多々あります。
子どもが大きくなってくると、親に相談することも減ってしまうかもしれません。
ママやパパも精神的に辛くなることもあると思いますが、子どもと一緒に悩む時期も期限があると思い、無理のない範囲で一緒に子育てを楽しみましょう。