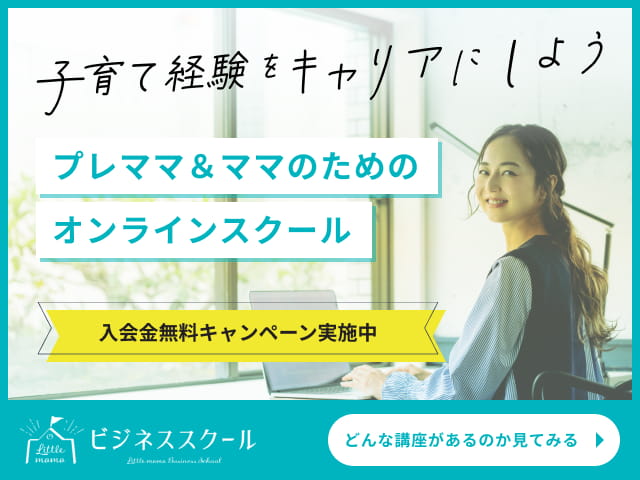キャリアWeb記事
あなたも利用できる!0歳児ママが1泊3,000円でぐっすり眠れる施設とは

「赤ちゃんとの生活リズムに気持ちが追いつかない・掴めない・不安がある」「赤ちゃんのお世話だけで一日が終わり、自分の睡眠時間がなさ過ぎる」「孤立してるようで辛い・苦しい」、そんな想いを抱えていませんか?
今回はそんな頑張ってるママを解放してくれる施設や事業、申請予約の流れなどをお伝えしたいと思います。
他にも筆者が利用した赤ちゃんの一時的なお預け場所も5つご紹介しますので、これから出産を控えているママや0歳児を育てているママはぜひ参考にしてみてください。
目次
産後ケア事業とは

出産後1年未満のママと赤ちゃんが対象の、心身回復と育児支援を目的とした施設・サービスで、大きく3つのスタイルに分かれます。
- 宿泊型(ショートステイ)
- 日帰り型(デイサービス)
- 訪問型(アウトリーチ)
主な支援内容としては、健康管理や母乳のケア・育児相談や指導・体重測定・発育や発達のアドバイス・沐浴方法や皮膚の手入れのアドバイスなどで、母親の希望に沿って赤ちゃんと別室・同室の選択が可能です。
母子別室の宿泊は生後2ヶ月未満に限る施設もあったりと、施設によって条件が異なるため、利用する前に問い合わせるといいでしょう。
産後ケアの利用内容と利用料

今回は筆者の住民票がある北九州市を例にしてお伝えしますが、住民票のある市区町村でのみ、通算7回まで以下の料金で利用可能です。
8回目からは設定自体を設けていない施設が多く、自費になる為1泊約3〜5万円と高額のようですが、令和6年に改正が入ったようなので、詳しくは利用する前に問い合わせるといいでしょう。
産後ケアの利用内容
- 宿泊型 1泊2日(10時〜翌10時)・3食
- 通所型 6〜7時間(9〜17時の間)・1食
- 通所型(短時間・生後4ヶ月未満) 2〜3時間
- 居宅訪問型 2〜3時間(9〜17時の間)
利用料
- 宿泊型:一般世帯 3,000円 / 減免世帯 1,000円
- 通所型:一般世帯 1,000円 / 減免世帯 300円
- 通所型:一般世帯 500円 / 減免世帯 150円
- 居宅訪問型:一般世帯 1,000円 / 減免世帯 300円
施設詳細・予約申請の流れについて

実施施設については市区町村のホームページに記載がありますので、インターネットで【ご自身の住民票がある市区町村名+産後ケア】を検索すると確認できます。
北九州市の場合は、施設に問い合わせ後予約→利用登録申請書記載という流れでした。
予約申請についても市区町村で流れが違うようなので、ぜひホームページで確認してみてくださいね。
その他、赤ちゃんの一時的な預け場所

ファミリーサポートセンター
子育てを「支援してほしい方」と「支援してくださる方」が会員となり、保育施設等への「送迎」や学校の放課後の「預かり」、保護者の急用や急病時、軽度の病児の「預かり」などを地域の力で支え合う事業
一時保育事業
保護者などのパート就労や疾病、出産及び育児リフレッシュなどの理由により、一時的に家庭での保育が難しくなったお子さんを、保育所でお預かりする制度
ベビーシッター
保護者の代わりに、子供の世話をする専門の在宅保育サービス
子育て支援施設
育児中の家庭をサポートするための施設やサービス
産後ケアホテル
出産後のママが育児や自身の回復に専念できるよう赤ちゃんを預かり、心身のケアや育児相談を行う宿泊施設
産後ケアの利用を検討されている方へ

「条件が合わなかった…」「予約が埋まっていて受けられなかった…」と悔やまないためにも、早めに【ご自身の住民票がある市区町村名+産後ケア】と検索をして、相談することをおすすめします。
初めての出産育児は未知の世界だから、不安や怖さが出てきますよね。
私もその一人。みんな同じ新米ママです。
赤ちゃんのお世話については、産婦人科で数日にわたり教わる機会もありますが、赤ちゃん一人ひとりで特徴も対応も全て違います。
だからママは迷い、考え、身を粉にして赤ちゃんを守ろうとします。
本当にお母さんって努力と愛情の塊だと私は思います。
だからこそ頼りましょう!学生時代、答えややり方が分からない時は先生を頼りましたよね?
ママになって分からないことがあったら、助産師さんや看護婦さん、保育士さんを頼って制度を利用しましょう!
そのために産後ケア事業が作られたのですから。
ただ、各市町村によって助成制度などの違いがあるようなので、ご自身の納得がいく制度を選ぶのが一番だと思います。
産後その足で宿泊を考える方もいらっしゃったりと、産後ケアにはさまざまな組み合わせや選択肢があります。
ご自身のお考えのもと無理のないよう状況に合わせて調整されてくださいね。
筆者の場合、産後は心が安定しなかったため最初の数ヶ月は実家に頼りましたが、自身の通院やハローワークなど各種手続きのために外出したい時はファミリーサポートセンター(1時間800円)、家の掃除や自分の頭の中をスッキリさせたい時は一時保育(1日2,000円)を利用したり、子育て支援室で子どもを見てもらっている間に、医療事務や手話を受講することもありました。
ここでお伝えした料金は筆者が利用していた北九州市のものですが、身近にどんな制度があって、どのくらいの料金帯なのかは、お住まいの市区町村の役所で聞くことができます。
10年前のあの頃、自分と向き合う時間をとったおかげで今では育自を楽しめるようになりました。
どうかご自身だけで抱え込まず、産後ケアという制度を利用し、楽になれる選択肢を増やすことでご自身と赤ちゃん、そして家族を守っていきましょう!
※本記事は、令和7年9月時点での情報です。最新の情報は必ずご自身で公式サイトなどでお調べください。