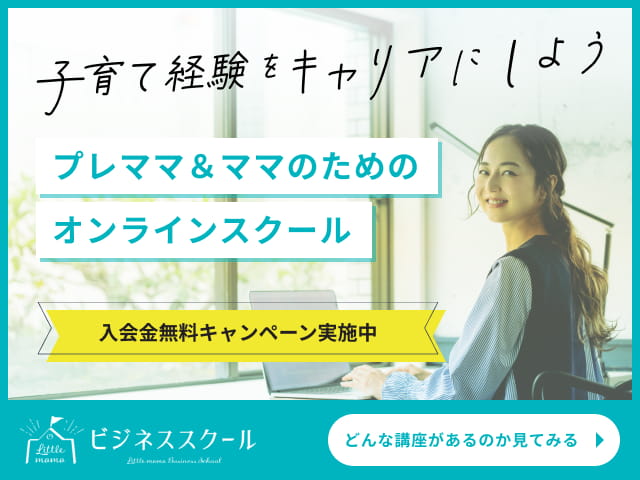キャリアWeb記事
【実体験】小学生ママに必要な3つの心構え!入学前に知っておきたいポイント

4月は新生活のスタートの季節。
期待と喜びに胸がふくらむ一方で、不安や心配を感じる方も多いのではないでしょうか。
新しい環境に飛び込むお子さまはもちろん、親御さんにとっても、子どもとのかかわり方や生活の変化に戸惑うことがあるかもしれません。
この記事では、昨年「小学生の母」となった筆者が、実際に体験したことをもとに、「小学生の母として大切だと感じたこと」をご紹介します。
目次
親同士の距離感、先生との接し方…不安だらけの小学校生活スタート

2024年4月、長男が小学校に入学しました。
先輩ママからは「小学生になると、幼稚園のときよりも情報が少なくなるから大変だよ」と聞いていましたが、
「入学後すぐに懇談会もあるし、きっと大丈夫だろう」と軽く考えていました。
ところが――
実際に懇談会に参加してみると、出席していた保護者はクラスの半分以下。
担任の先生によると、共働き家庭が増えている影響もあり、年々参加者は減少傾向にあるそうです。
さらに、コロナ以降は学校行事やPTAの集まりも縮小され、親が学校へ足を運ぶ機会は月に1回あるかないかという状態。
「気軽に話せるママ友ができたらいいな♪」と期待していた私でしたが、
懇談会では、誰がどの子の保護者なのかさえわからないまま終わってしまいました。
また、幼稚園時代は送り迎えのタイミングで先生と話す機会がありましたが、
小学校では子どもがひとりで登下校するため、先生と直接話すことはほとんどありません。
つまり、学校での様子はすべて子どもから聞くしかないという、なかなか不安な状況でのスタートとなったのです。
鵜呑みにしない!子どもの話を正しく聞く“5W1H”のコツ

幸いなことに、近所には同じ小学校に通うお子さんを持つ先輩ママがいたので、学校行事などで分からないことがあれば、気軽に相談することができました。
ただ、問題は別のところにありました。
それは、子どもから聞く学校での出来事が、どこまで本当なのか分からないということ。
たとえばある日、長男が突然こう言いました。
「〇〇さんに叩かれたんだよ」
「え?どうして?いじめ!?大丈夫なの!?」と焦って話を聞いてみると、
実際に叩かれたのは長男ではなく、その場にいたお友達。
それをあたかも自分のことのように話していた、ということがあったのです。
また、長男自身が相手を怒らせるような言動をしていたにもかかわらず、
まるで“自分が一方的な被害者”のように話していたこともありました。
このように、「誰が・何を・どうしたのか」があいまいなまま話をされると、
勘違いして受け取ってしまい、危うく学校を巻き込むトラブルになりかけたことも。
話し方・聞き方の工夫:「5W1H」を意識
そこで我が家では、「5W1Hを意識して話す&聞く」というルールを取り入れることにしました。
「5W1H」とは、以下の6つの疑問詞の頭文字をとったものです。
When(いつ)
Where(どこで)
Who(誰が)
What(何を)
Why(なぜ)
How(どのように)
この6つを意識して話すことで、
「誰が」「どこで」「いつ」「何をした(された)」のかが自然と整理され、会話がグッと分かりやすくなります。
私は長男に、「話すときはできるだけこの6つを意識して話してね」とお願いし、
こちらも「話が見えづらいときは、5W1Hに沿って質問する」ようにしました。
その結果、話の全体像が見えてくるようになり、
余計な心配や誤解、トラブルを防ぐことができるようになったのです。
さらに、「How(どのように)」を使って、
「そのときどう感じたの?」と感情に目を向けることで、
「学校に伝えるべきか」「少し様子を見るか」といった対応の判断もしやすくなりました。
備えあれば憂いなし!“いざ”に役立つ補修テクは覚えて損なし

次に悩んだのは、「学校用品がすぐ壊れる」という問題でした。
入学して1か月もしないある日、長男からこう言われたのです。
「教科書の表紙、全部とれた!」
…驚きすぎて、もはや笑うしかありませんでした。
その後も次々と壊れていくものたち…
買ったばかりの靴に穴が開く。ズボンの膝やポケットが破ける。もう、キリがありません。
毎回怒っていても仕方ないので、私は「補修テクを備える」ことにしました。
今回はその中でも、特に役立ったアイテムを2つご紹介します。
① 本の補修テープ
教科書やノートが破れたとき、ついセロハンテープで補修してしまいがちですが、
時間が経つと黄ばみやベタつきが出てしまいますよね。
そこで便利なのが「本の補修テープ」。
透明ビニールのような素材でできており、耐久性・耐水性に優れていて、
摩擦や湿気にも強いので黄ばみやベタつきが出にくいのが特徴です。
文房具店やオンラインストア、100円ショップなどでも手軽に手に入ります。
これがあれば、教科書が破れて帰ってきても、怒らずにすむ“心の余裕”が生まれますよ。
② 洋服の接着剤「裁ほう上手」
長男は元気いっぱい。
気がつけばズボンの膝やポケットに穴が……なんて日常茶飯事です。
でも、毎回縫うのは大変。どうせすぐサイズアウトしてしまうし、直すのも時間がもったいない。
そんな時に見つけたのが、アイロン不要で洗濯OKの布用接着剤『裁ほう上手』です。
オンラインストアや一部のコンビニ、手芸店などで購入可能で、使い方もとっても簡単!
・穴の開いた部分の裏から、同系色の布をあてる
・接着剤を塗って、ぎゅっと貼り付ける
靴の小さな穴なら、綿を詰めてふたをするように接着すればOK!
気軽に補修できるようになったおかげで、活発な長男に対してのイライラもずいぶん減りました。
「形あるものはいつか壊れる」という心構えと、
「壊れたときの対策」を少し用意しておくだけで、学校用品が壊れるたびに感じていたストレスをグッと軽減することができました。
「待つ前提」で声をかけよう!子どもの失敗は成長のタネ
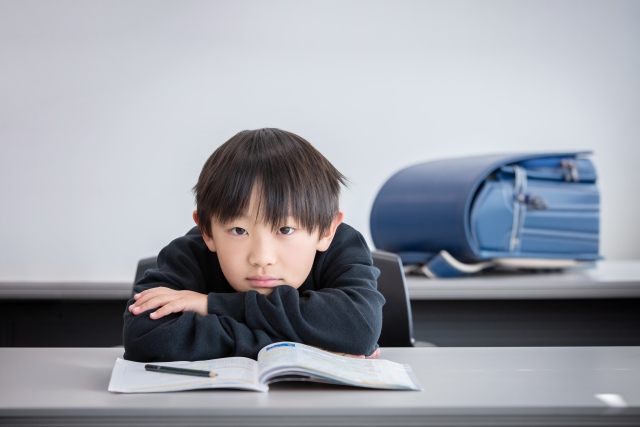
この1年で一番悩んだのは「どこまでお世話するべきか」ということ。
朝の支度、宿題、翌日の準備。
どれも小学生になったら子ども自身でできるようになってほしいことですが、完全に任せると、とにかく時間がかかる!
でも、親がずっと手を出していては、いつまでたっても自立できない…。
そんなジレンマの中で、私が意識したのは、
「子どもが1人でも用意しやすい環境を整えること」でした。
ここでは、特に効果があった3つの工夫をご紹介します。
①「いつするか」を自分で決めさせて責任感を育てる
入学してすぐ、長男と話し合って決めたのが「宿題をいつやるか」ということ。
「ごはんの前?あと?お風呂のあと?」「早く済ませた方がラクだよ〜」など、
いくつか選択肢とメリット・デメリットを伝えた上で、長男が自分で決めるようにしました。
あとはひたすら見守るのみ。
時には寝る時間ギリギリになって焦る日もありましたが、それも学びのうち。
「これじゃダメだ」と本人が気づいて行動を見直すようになり、
自分なりのルーティンで宿題をこなせるようになりました。
今では「宿題やったの?」と私が声をかけることも、ほとんどなくなりました。
② 張り紙+リズムで忘れ物対策!
小学生になると持ち物が一気に増えますよね。
そこで取り入れたのが、「視覚」と「リズム」を使った声かけです。
まずは、玄関のドアに「持ち物リスト」の紙を貼ります。
・毎日持っていくものは黒字
・イレギュラーな持ち物は赤字
など、パッと見て分かる工夫をしました。
慣れてくると、どうしても見落とすことも出てきます。
そんな時は「ハンカチ〜♪ ティッシュ〜♪」とリズムにのせて声かけしたり、
替え歌にして楽しく伝えたりするようにしました
明るい気持ちで登校してほしいから、
できるだけ怒らず、楽しい雰囲気を心がけました。
③ 忘れても怒らない「大らかさ」が成長を支える
いくら工夫しても、忘れるときは忘れます。
そんなときに私が心がけているのは、「怒らない」「責めない」こと。
子ども自身、学校で困ったり恥ずかしい思いをしているはず。
そこで家でも怒られてしまったら、ますます自信を失ってしまいますよね。
だから私は「忘れちゃったんだね。明日はどうしようか?」とだけ伝えるようにしました。
すると、「今のうちにランドセルに入れておく!」と自分から行動するように。
今では、寝る前には翌日の準備を済ませる習慣がしっかり身についています。
最近では、忘れっぽい私に「お母さん、〇〇の用意した?」と確認してくれることも!
よく考えれば、大人だって失敗もするし忘れ物もします。
子どものちょっとしたミスに対して、
「失敗は成功のもと」と割り切って、大らかに見守る。
それが、子ども自身の考える力や行動力を育てることにつながるんだなと、心から思いました。
待つってむずかしい!“母の器”を育てられた1年間

この1年間、不安だらけの小学校生活に向き合う中で、私はたくさんイライラしながら
「どうしたら必要以上に怒らずにすむのか?」を何度も考えました。
その答えは…
「子どもを信じて、“いざ”という時に対応できる準備をしながら待つこと」。
子ども同士のトラブルも、きっといつかは自分たちで解決できるようになるはず。
学校で使う物の扱いも、やがて丁寧になっていくでしょう。
忘れ物や失敗だって、経験を重ねるうちに少しずつ減っていくものです。
私が感じた「小学生の母に必要なこと」は、
大らかな気持ちで見守ること、
そして毎日子どもが楽しく過ごせるようサポートすることでした。
これから反抗期に入ると、素直に言うことを聞かない日も増えてくるかもしれません。
でも、そんな時こそ“大らかな気持ち”でいることが、
子どもの心の安定にも、親である自分の余裕にもつながると実感しています。
新しい環境に慣れるまでは、不安や心配が尽きないかもしれません。
それでも、たった一度の小学校生活。
ぜひお子さんと一緒に、笑顔で楽しく過ごしてくださいね。